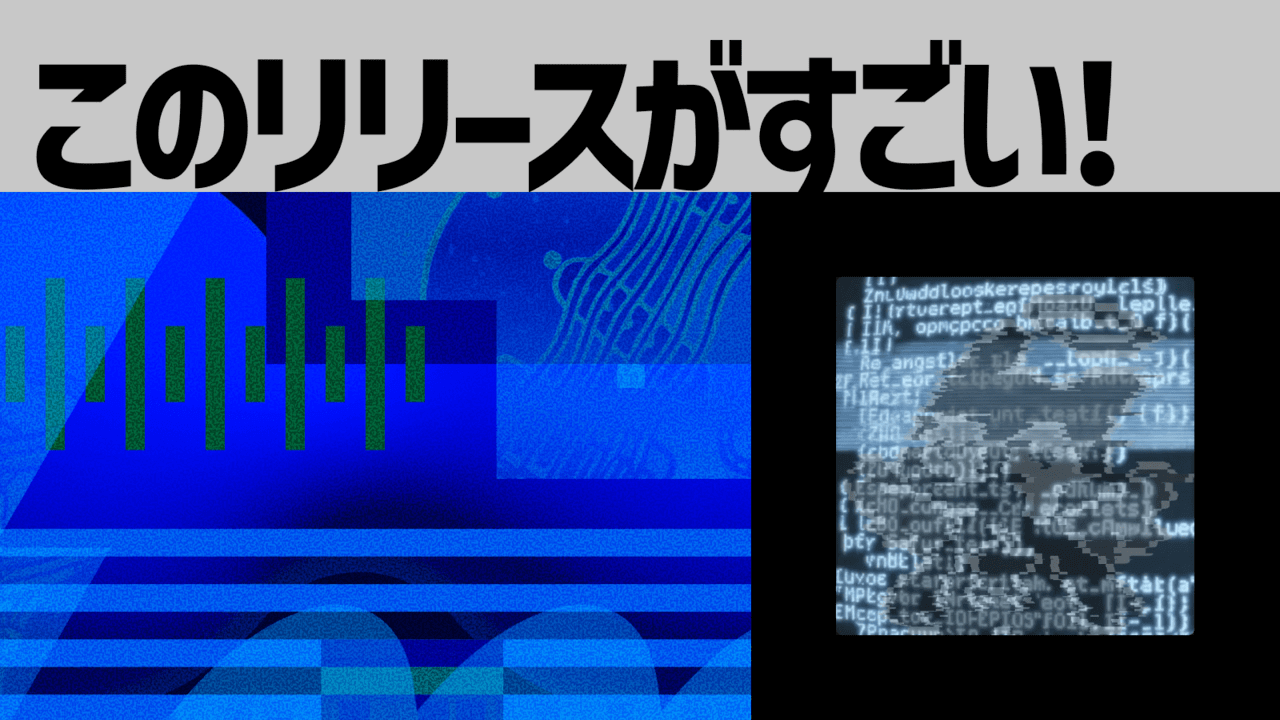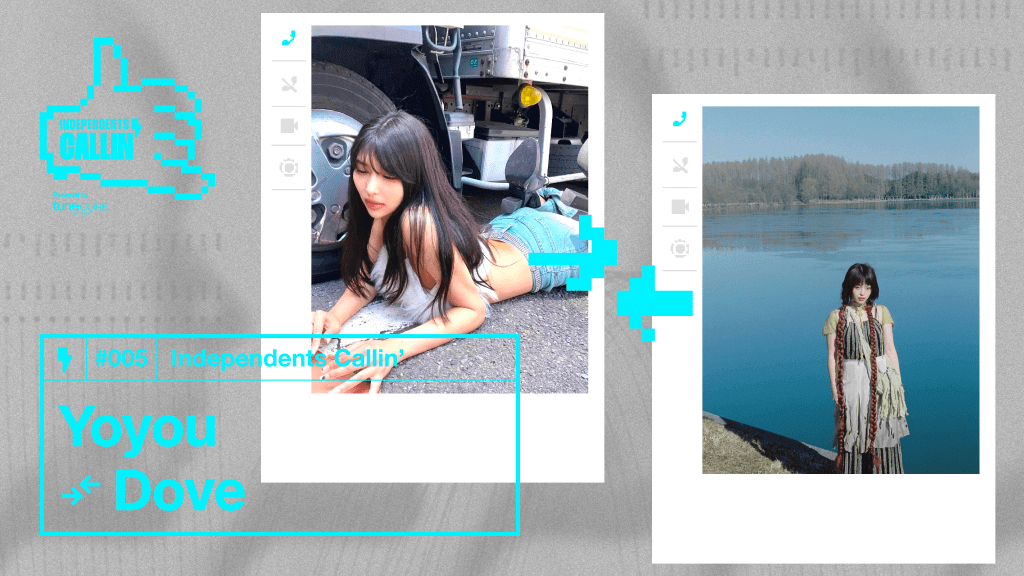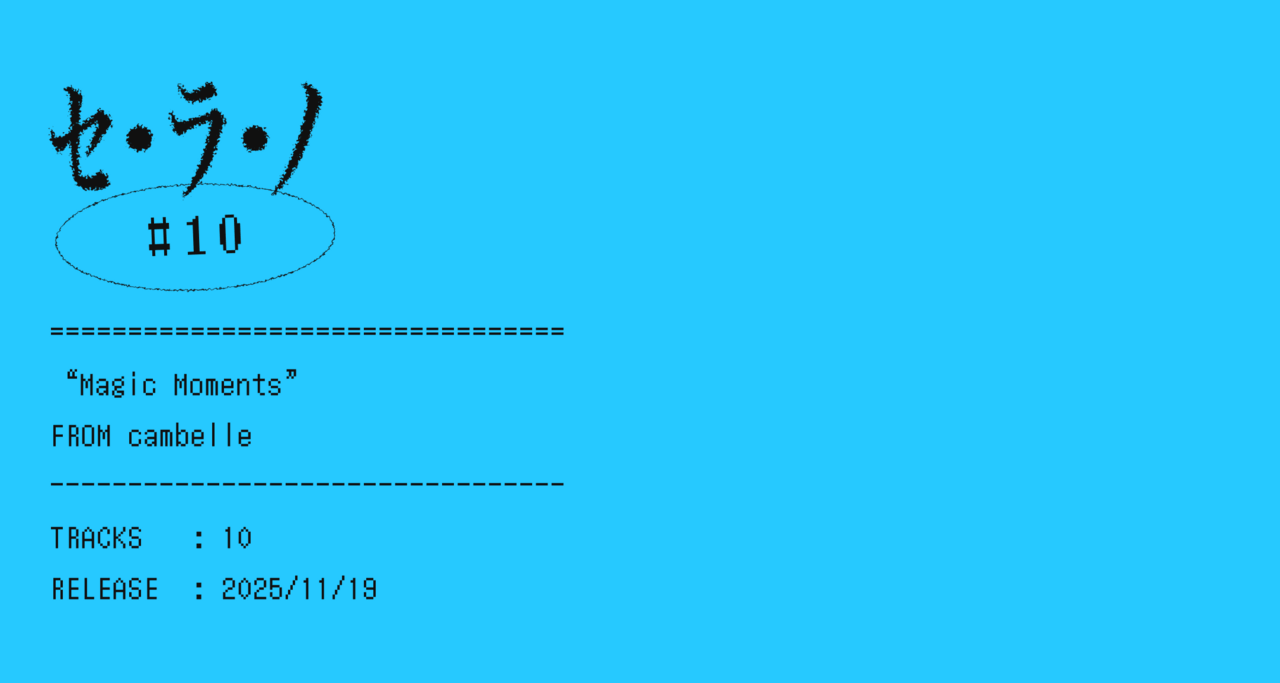【連載】アーティストのための法と理論 ビギナークラス — エピソード11「アーティスト名やロゴ等に関する権利」
■清水航弁護士による解説
アーティスト名に関する権利
アーティストやグループの人気が上がっていくと、その名前が入ったグッズ等にも魅力を感じる人が増えていき、アーティスト名やグループ名(以下では簡略化して「アーティスト名」といいます)にも一定の経済的価値が生じてきます(このようなことをアーティストが「顧客吸引力」を獲得すると表現します)。
このように経済的価値を有するに至ったアーティスト名についてはそれを利用したいという人も増えてきますが、アーティスト名にも複数の権利や法律が関係します。主には以下に記載するものが挙げられますが、アーティスト名を利用しようとする者は、これらについていずれも問題が生じないように気を付ける必要があります。
① 商標権
② 不正競争防止法
③ パブリシティ権
④ 著作権
商標権について
商標権は、特定の商品やサービスとの関係で名称やロゴ等の標識を独占的に使用できる権利で、この権利を取得するためには特許庁に対して一定の出願手続をする必要があります。例えば、「被服」について、アーティスト名の商標権を取得しておくと、他の人に対してそのアーティスト名を印刷したティーシャツを販売することをやめるようにいうことが出来るわけです。但し、ここでは細かく言及しませんが、商標権の効力が働くのは「商標的使用」といって、商品等の出所がどこであるかを識別できるような形でアーティスト名が使われている場合に限られるので、書籍や雑誌についてアーティスト名の商標権を取得したとしても、出版社が当該アーティストに関する記事を一切書けなくなるという話ではありません。
ここで大事なこととして、商標権は「先願主義」といって、基本的に先に出願手続をした人が取得できる権利ですので、自分がアーティスト名として使っていても第三者に取得されてしまう可能性があります。しかも、商標権はあくまで商品やサービスの種類ごとに取得されるものであって「アーティスト名」としてといった限定があるわけではないので、例えば衣服について、同名のブランドが設立されて商標権を取得されてしまえば、物販のティーシャツにその名前を使ってはいけないと言われてしまう可能性があります(なお、このようなことからアーティスト名を決める段階で、物販販売時に他人の商標権に抵触しないかを調査することもあります)。
とはいえ、特にアーティスト名が一定程度有名になっている場合には第三者が商標権を取得したとしても、その有効性や効力を争う余地はありますし、商標権の取得には特許庁に対する手数料のほか、弁護士や弁理士などの専門家への委託料もかかります。そのため、どの段階で商標権を取得するかは、アーティストの活動状況(知名度)、他人が出願する名称と被る可能性、当該アーティスト名への思い入れの強さ等の諸事情を踏まえて総合的に判断することになります(なお、アーティストがプロダクションと契約した場合には、プロダクション側で商標権を取得することが多いです)。
また、以下の場合等には商標権の取得が認められない点にも留意が必要です。
ア.) 一定の知名度があるアーティストの名称について、レコード等を対象として出願する場合
イ.) 関連する分野で一定の知名度がある同名の人物がいて、当該人物の承諾を取得できていない場合
不正競争防止法について
商標権を取得していない商品等についても、一定の場合には、不正競争防止法という法律にもとづいて商標権を取得しているのと近しい態様で、アーティスト名の使用をやめるように請求することができます。
もっとも、この場合には、アーティスト名に相応の知名度(「周知性」あるいは「著名性」といいます)が存在することが前提となることに留意が必要です。
パブリシティ権について
日本の法律に直接的な記載はありませんが、裁判例上で認められているものとして、パブリシティ権という権利があります。パブリシティ権とは、人の氏名、肖像等が持つ「顧客吸引力」を独占的に利用する権利とされており、アーティスト名もこれら人の氏名、肖像等の対象に含まれます。そのため、アーティスト名を主に以下の方法で勝手に使用する場合に侵害になるとされています。
ア.) それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合(写真集等)
イ. ) 商品等の差別化を図る目的で商品等に付する場合(海賊版グッズ等)
ウ.) 商品等の広告に使用する場合
パブリシティ権は、商標権のように出願手続等を行わなくても各アーティストに発生します。もっとも、まだ知名度が低いアーティスト等にも権利が発生していると言えるのかは議論のあるところで、裁判例の一般的な傾向としては、既に一定の顧客吸引力が発生していること(一定のファンが存在すること)が必要とされているものと思われます。
著作権について
まず注意していただくこととして、アーティスト名のような固有名詞自体に著作権が認めてもらえることはなかなかありません。したがって、他人が自分のアーティスト名を勝手に使っていたとしても、アーティスト名を使用しているということ自体をもって著作権侵害であると主張することは難しいということになります。
これに比べると、アーティスト名のロゴマークについては著作権を認めてもらえる可能性があります。しかしながら、裁判所は、文字の表記の仕方に簡単に著作権を認めてしまうと影響が大きいと考えているのか、ロゴマークについても比較的高いハードルが課している印象があり、例えば比較的最近の裁判例では、「顕著な特徴を有するといった独創性」や「識別機能という実用性の面を離れて客観的、外形的に純粋美術と同視し得る程度の美的鑑賞の対象となり得る創作性」が必要としたものがあります。もっとも、これらの文言が具体的に何を意味するのか、またそもそもこのような要件を必要とすることが適切であるのかということについては議論のあるところですので、個別の判断は弁護士等の専門家であっても難しい場合が多いです。とはいえ、少なくともこれまでの裁判例の傾向としては、イラスト的な要素がなく一般的な書体に近いようなロゴマークについては著作権が認められない可能性が高いということは知っておくとよいでしょう。
今回の内容をはじめ、音楽に関する法的知識を身につけたい方は下記のバックナンバーもぜひチェックしてみてください!
『アーティストのための法と理論 – Law and Theory for Artists』バックナンバー
https://magazine.tunecore.co.jp/taglist/law-and-theory-for-artists/