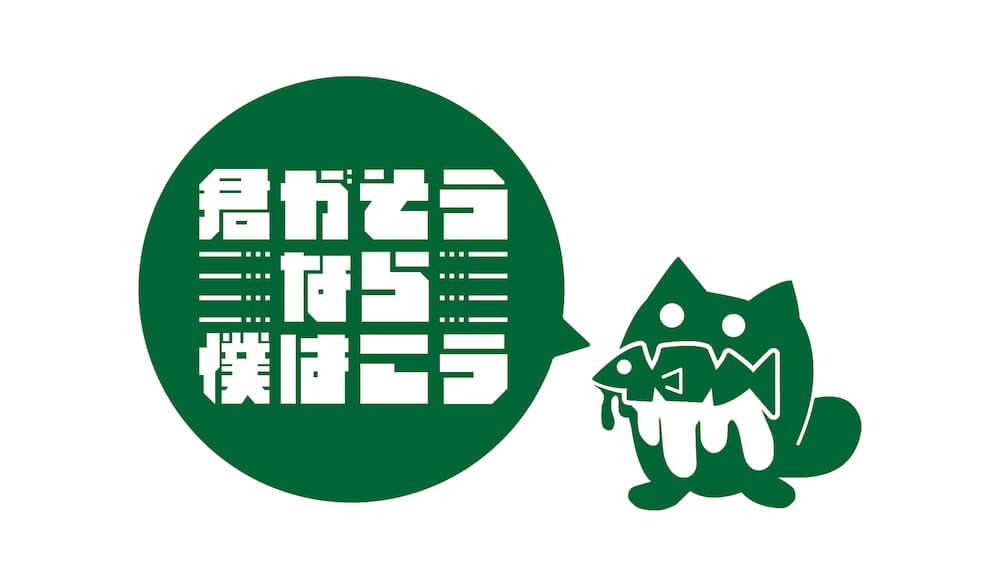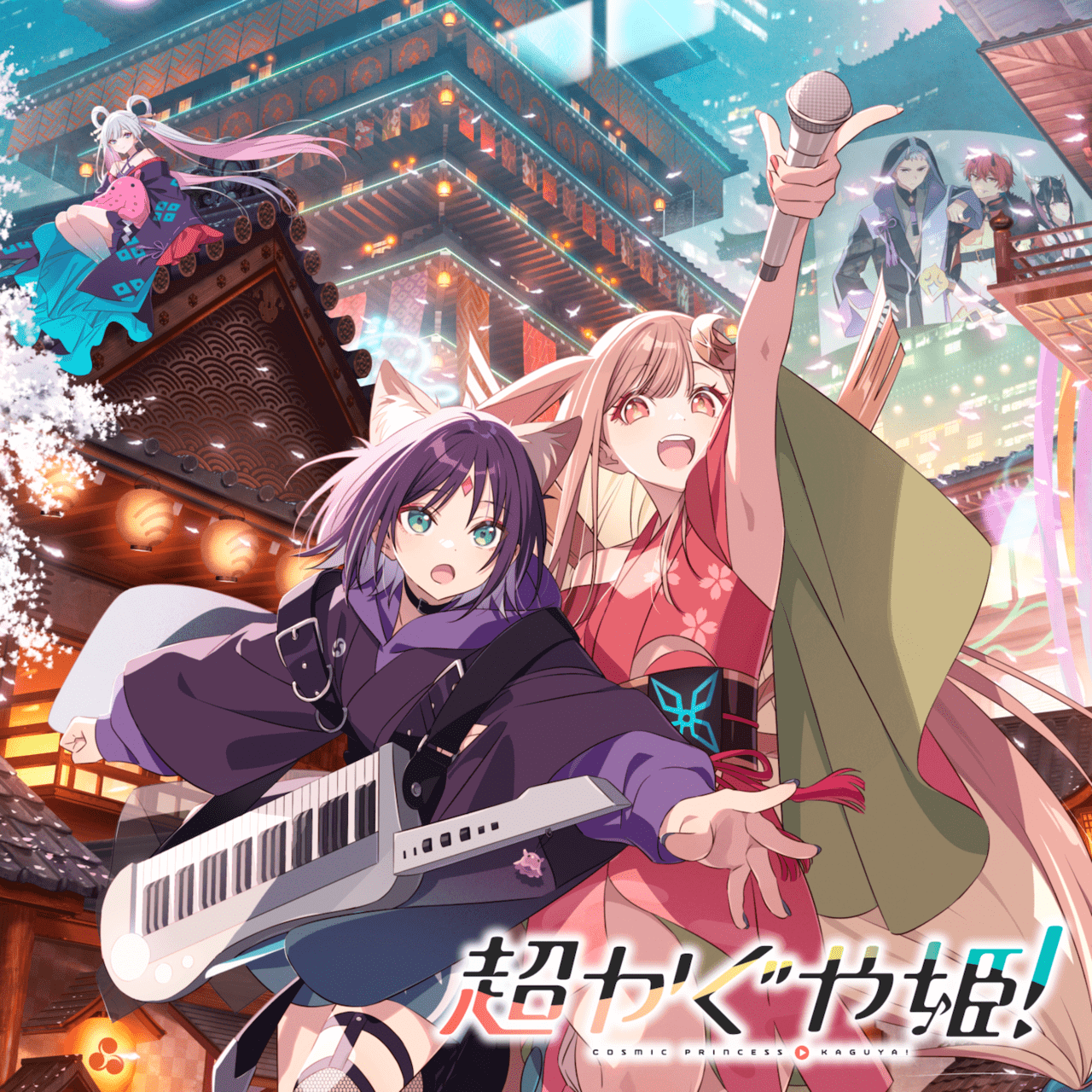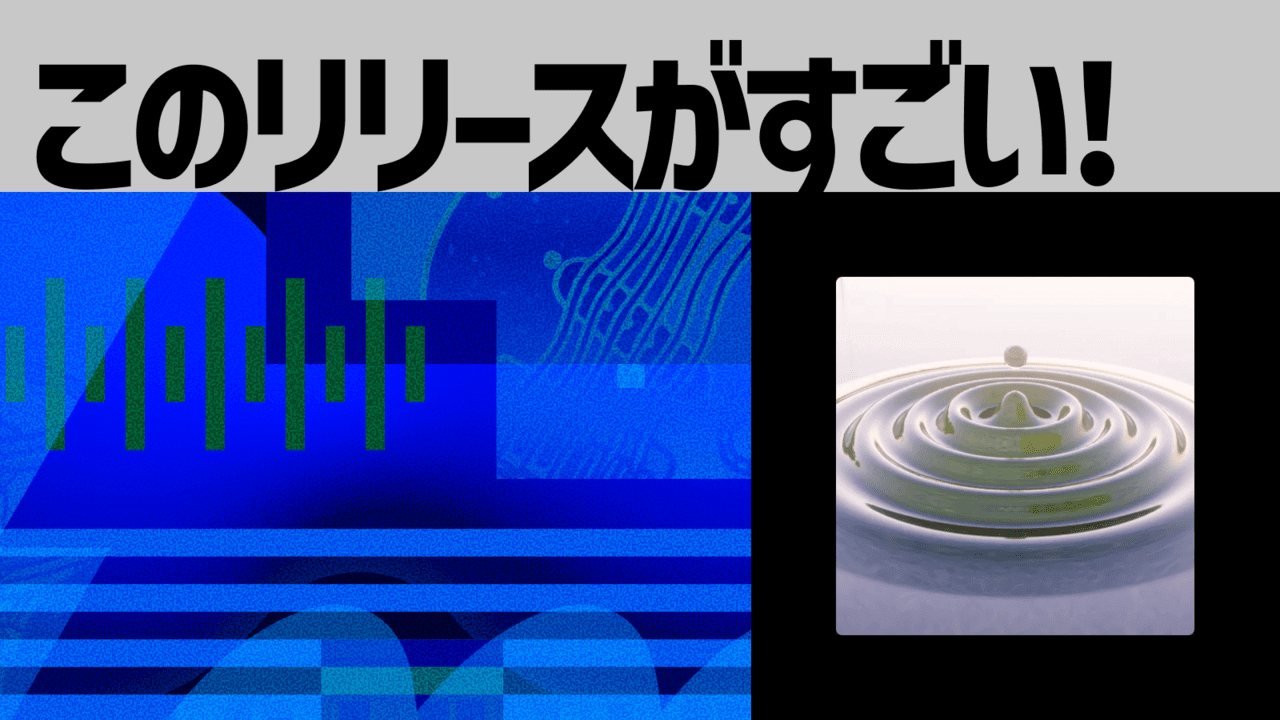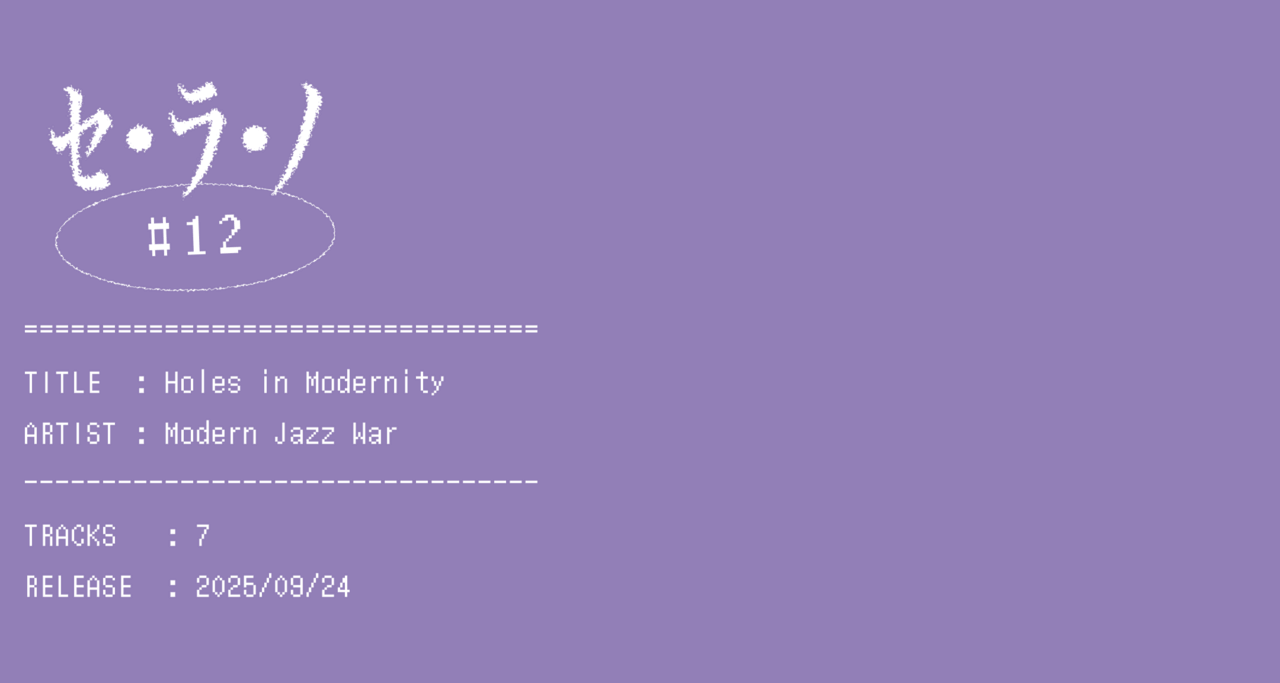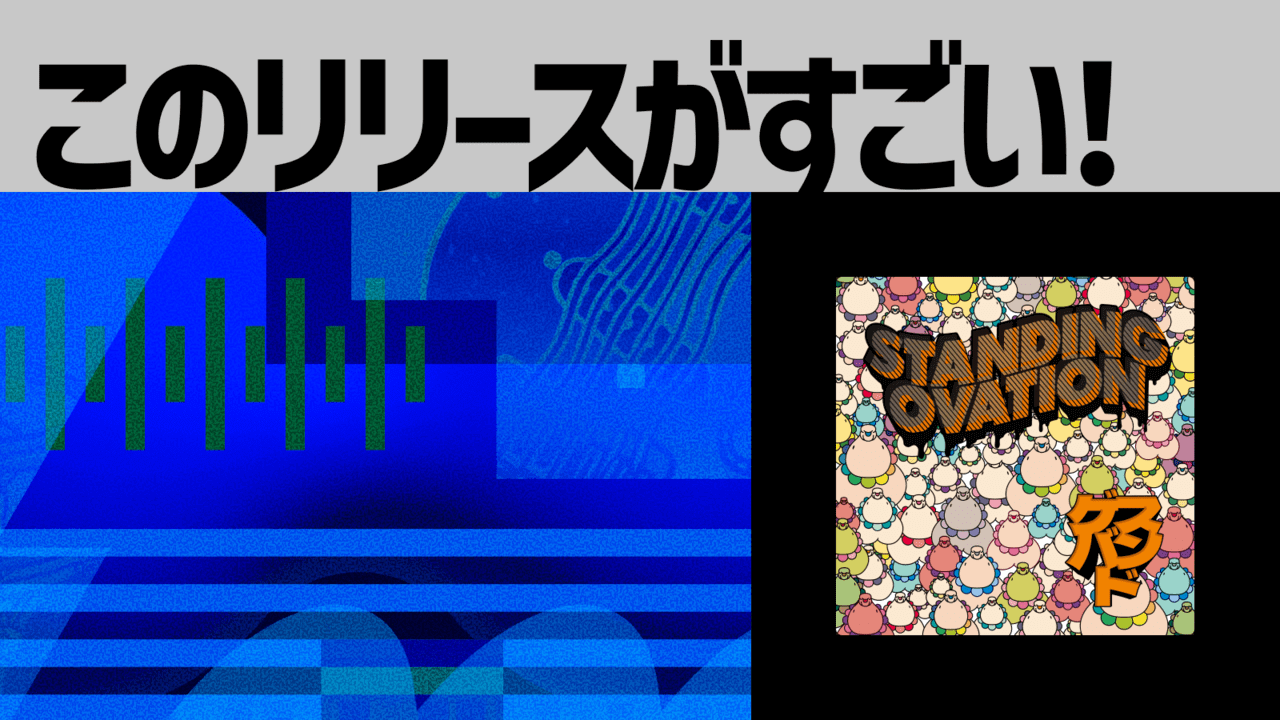吉武健 (Dead Funny Records オーナー) インタビュー | 福岡から良質な音楽を世界に発信する気鋭のレーベル
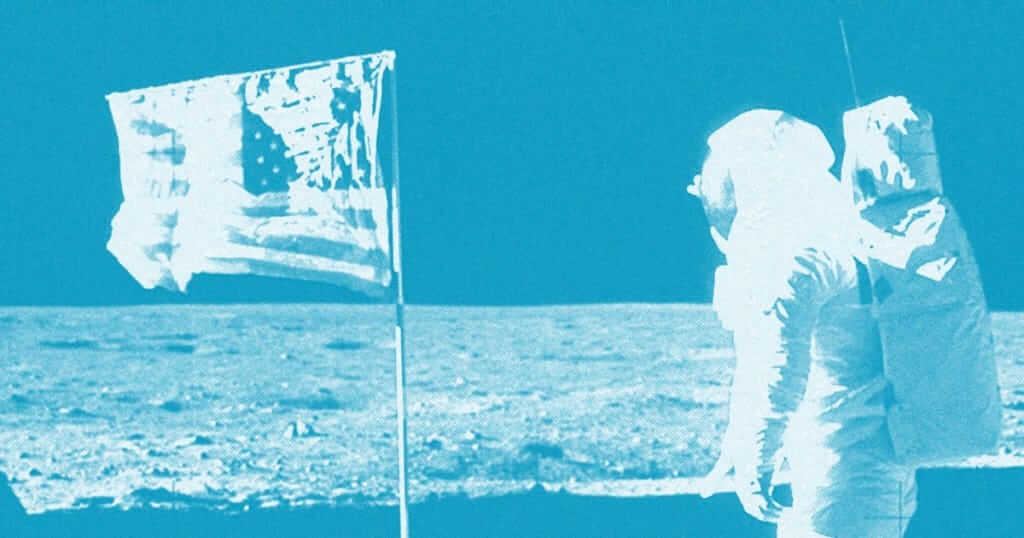

東京を離れて福岡に拠点を構えるDead Funny Records。インディーズシーンを賑わす新人アーティストたちを、音楽中心地の東京を離れ、福岡からいち早く音楽マーケットに送り出し続けている音楽レーベルだ。つい先日も、Apple Music で今最も注目すべき新人アーティストを特集する企画「今週のNEW ARTIST」に、Dead Funny Recordsがあつかう北海道在住の無名の新人バンド・mooが選出されたばかりだ。

このように徐々にその存在感を確かなものにしているDead Funny Recordsのレーベルオーナー吉武健さんに話をうかがった。
きっかけは熊本のひとつのバンド
——まず、最初にDead Funny Records設立の経緯や背景を伺っていきたいのですが、レーベル設立当初から、福岡を拠点にしながら活動されていたのでしょうか?
そうですね。最初からずっと福岡です。レーベル立ち上げが2012年なので、来年で5周年になります。
——どんな経緯で、福岡でのレーベル設立に至ったんですか?
僕個人はもともと今も親会社が同じMOORWORKSというレーベルで、海外アーティストの国内版リリース契約や、ライセンス流通の仕事をやっていたんです。ただそれも、渋谷にオフィスがありながら、福岡でやっていたんですけど(笑)。
——そうだったんですね。
もともと会社全体に、そういう傾向があるんです(笑)。MOORWORKSのレーベルオーナーをやっている、斎藤という社長がいるのですが、彼は仙台を拠点にしつつ、全国各地を飛び回って、月の三分の一を東京で過ごすようなタイプで。今も、会社(Some Echoes株式会社)としての正式なオフィスは渋谷にあるんですけど、そこにはレーベルスタッフは誰もいなくて、電話代行のスタッフさんだけがいる状態で(笑)。
——なるほど。
もとがそういう感じだったので、僕が福岡でDead Funny Recordsを運営していくというのも、特に違和感なく、自然な形でスタートできたというか。
——どうして、あえての“福岡”なんでしょうか?そこになにか、明確な理由があったりするんでしょうか?
う〜ん…。(申し訳なさそうに)正直、特にないというか、強いて言うなら、僕が住んでいたからっていうぐらいかもしれません(笑)。
——あれ、そうなんですか?勝手ながら、そこに福岡である理由やこだわりがあるのかなぁなんて、想像していたのですが。
福岡で活動したくて始めた、というよりは、結果として福岡で活動していくことになった、という部分が大きいですね。レーベルを立ち上げるきっかけにもなったtalkというバンドが、熊本にいて。
——福岡ではなく?
はい、熊本です。熊本と福岡って、(地理的に)近いといえば、近いんですよ。僕はUS志向のバンドが当時から好きなのですが、福岡にはそこまでUS志向のバンドがいなくて。だから必然的に、音楽的な好みが近しい、隣の県の人やアーティストたちと仲良くなっていくようなところがあって。
——そうか。福岡と熊本って、隣の県ですもんね。
意外と近いんです(笑)。それで、彼ら(talk)の勢いがものすごくて、自主制作で出していたEPが手売りで直ぐに500枚完売しちゃうような状況で。その様子を近くで見ていて、こんなにいい音楽をやっていて、自分たちでここまでCDを売って、ファンにも恵まれている彼らが、外に出ていけないのは勿体なぁと感じて。
——良いアーティストの良い音楽が、一部のひとだけにしか届かない状況だったと。
はい。その状況が、すごく勿体ないと思って。それで最初はMOOR WORKSを通じて全国流通できればとも考えたんですけど、海外アーティストを扱うレーベルから、日本のアーティストが1 組だけ出て行くのも不自然かなと。だったら日本のアーティストを流通させるレーベルを、別に作ったほうがいいんじゃないかと思って。それで始めたレーベルが、Dead Funny Recordsだったんです。だから元々は、熊本にいたその1組のバンド(talk)を世の中にもっと出していきたくて、福岡を拠点に始めたレーベルですね。
——才能を秘めた地方で活動するアーティストを、次のフェーズに乗せるために始まったレーベルなんですね。
格好良く言えば、そうですね(笑)。スタート地点は、そこです。でも結局レーベルを始めると、経済的な意味でレーベルを運営していかなくちゃいけなくなるので。「九州のアーティストをリリースするだけじゃ足りない!」となって、関西と関東のアーティストも、徐々にリリースするようになっていって。
——たった1組のバンドのために、音楽レーベルを立ち上げる。それってすごく、思い切った判断ですよね。
だったんですかねぇ…(笑)。でも今思うと、当時は2chまとめ全盛期で、音楽まとめで『路地裏音楽戦争』っていうサイトがあったんです。これが音楽好きの間で無茶苦茶に流行っていて、そこに載れば(インディーズ音楽を)色んな人が聞いてくれるし、ものすごく売れていくという感じがあって。インターネットの力を借りて、地理関係や活動拠点を気にせずに音楽をやっていけるような空気感があったんだと思います。
インターネット上に住所を持つ感覚で
——今すこし話に出ましたけど、地方を拠点としてレーベル運営をしていくうえで、インターネットとの付き合い方は、設立当初から意識していたんでしょうか?
そうですね。むしろ自分の中では、「福岡で(レーベルを)やっている」というよりは、「インターネットの中でやっている」というイメージなんです。実際、福岡で活動しているアーティストで、僕たちのことを知っている人は少ないと思いますよ。福岡にはいるけど、住所があるのはインターネットという感じで。
——ネットレーベル的な感覚というか。
それに近いと思います。特にレーベルとしてのフットワークの軽さは、ほんとそれに近いですね。たとえばうちは、基本的にメールのやり取りですべての作業を進めていくんです。アーティストから(作品を)出したいという連絡をもらってから、店舗にCDが並ぶまでのやり取りを、すべてメールでやっていて。
——実際に作品が発売された後でも、アーティストと会わないってこともありますよね?
全然あります。バンドによっては、直接会うことを大事にしているバンドもいるので、そういったバンドに関しては直接会ったりしますけど、基本的には、オンラインのやり取りだけで。
——様子を伺うかぎり、それで「不便だな」と感じることって、ほとんど無さそうですよね?
うん。今のところ、ないですね。アーティストにとって、僕らのようなレーベルと付き合っていく良さは、いい意味で「割り切れる」ことなのかな、と思います。
——割り切れること、ですか?
はい。東京のレーベル、すごくいいと思うんです。マネジメントも任せることができて、イベントも企画できて、どんどんアーティストを上へ押し上げていく強さがあって。でも僕らは今、地方の福岡にいるので、東京のレーベルと同じことはできない。でも逆に何をやれるのかというと、「アーティストに自由を与える」ことならできるんじゃないかなと。流通をする、つまり、自分たちの販路で「売る」ってことは決定権を持ちますけど、それ以外は、アーティストに委ねることができて。例えば、僕たちが流通する作品は、すべてアーティストが原盤(マスターテープ音源の権利)を持っているんですよね。
——レーベルではなくて、アーティストが原盤をもっている。
はい。だから極端なはなし、僕たちで流通していたアーティストが、他のレーベルに移籍したり、他社から持って行かれたりすることも、十分起こり得るんです。
——そうですよね。
でも僕たちとしては、それでも全然オッケーで。むしろ、「そうなってほしい」ってぐらいに思ってます。最近も、PAELLASというバンドにCMオファーがあったんですけど、彼らの1作品目をうちからリリースしていたので、最初は僕たちに問い合わせがあって。そこで、「本人たちが自分でマネジメントしてるので、そちらにぜひ聞いてみてください」とご担当者をお繋ぎして(笑)。
——そんな流れが(笑)
でも大真面目に、彼ら(PAELLAS)が今、そういう規模のアーティストになっているのは、すごくうれしいんですよね。僕たちが「このアーティストは売れる」「このアーティストこそ売れてほしい」と思っていた人たちが、実際に売れていくのは、本当に爽快で。PAELLASのケースだと、彼らがそこにたどり着くまでに、最初にうちからファーストアルバム(『Long Night Is Gone』 2012年発売)をリリース出来たってことも、少しは役に立てたんじゃないかなと思いますし。
やっぱり、いわゆる東京の感覚でレーベルをするとなると、レコーディングだったり、イベント制作であったり、どうしてもコストが大きくなると思うんです。そしてそれを回収するために、たくさん売らなくちゃいけないし、売れるであろうアーティストを優先して流通させる構図が、どうしても出来あがってしまう。でも僕らは、その役割をアーティストと最小単位で切り分けてやっているので、そういう意味で、お互い健康的というか。
——本当にアーティストとの距離感を大事にしていると感じます。良い意味で、近すぎず、離れすぎず。でもいつも、遠目にどこからかは見ていて。
それでいいのか、ってはなしもありますけどね(笑)。でもそうやって、アーティストに自由にやってもらうことが、自分たちのレーベルのカラーになっていくのかもしれないなと。アーティストにとって、フットワークが軽くて、自由度が高くて、フラットに付き合えるレーベルになれれば。
——どちらかが一方を囲い込むではなくて、お互い機能を提供しつつ、共存していくというか。
話しながら気付いたんですけど、それはDead Funny Recordsの成り立ちが影響してるのかもしれないです。もともとはMOORWORKSとして、海外アーティストのライセンス流通をやっていたので、アーティスト本人とは会わずにインターネットでコミュニケーションをして、自由に活動してもらって、僕たちは粛々と国内で作品を流通させるのが仕事だったので。そのスタンスで日本人のアーティストに対しても付き合っているので、こういう温度感での、フラットな関係になっているんじゃないかと思います。ツアーのときにあって、「Oh! Yo!」「お前だったのか!」みたいな(笑)。
音楽を届けることに対して
——これまでお話を伺ってきて、レーベルとして、アーティストに対してフラットな関係であることと、そのフラットな関係性だからこそ、世の中に出せるような作品を出していくことを、とても大事にしていると感じました。
そうですね。まずはフラットな関係であることを前提にしつつ、当たり前のことかもしれないですけど、やっぱり作品を全国に流通させるかさせないかが、思っている以上に重要だったりするんですよね。そもそも、インディーズの音楽って、「音楽を追ってるひと」しか、聞かないわけで。だからそこに届ける意味って、少なからずあると思うんです。聞かないひとに押し付けているんじゃないですからね。
——たとえ母数は小さくても、そもそも「聞きたい」と思っているひとに届けるんだから、そこから広がっていく何かがあると。
はい。実際に、僕たちが流通をサポートしているインディーズ・アーティストからは、作品を出した後に、次のお話が来るようになったとか、ライブの誘いが来るようになったとか、そういう話をよく聞くんですよね。やっぱり、自分たちだけで自主でやっている範囲を超えて、「売り物」として正規の流通に乗せることから、はじめて通過できる壁というのは、あると思うんです。
——これからDead Funny Recordsとして、これから先、さらにどうなっていきたいのでしょうか?
憧れとするレーベルはありますね。たとえば、ニューヨークのCaptured Tracks(キャプチャード・トラックス)というレーベルがあって。レーベルとしてすごくスタンスが明確で、音楽性にも一貫性があって、しかもMac DeMarcoみたいなヒットアーティストもいて。多分、セールス的には厳しいアーティストもたくさん出していると思うんですけど、「Mac DeMarcoでなんとかする!」みたいな(笑)。でもそういうスタンスだと、レーベルとして潰れないし、長く続いてく。それに「キャプチャードだから買おう!」っていうお客さんも、きっとたくさんいると思うんです。あとは日本だと、Second Royal Recordsさんですよね。京都を拠点にしながらホテルメキシコっていう、海外の音楽サイトでも取り上げられるような素晴らしいアーティストをリリースしてて、今もHomecomingsのようなアーティストを生み出してインディーズシーンをすごく楽しくしている。
——なるほど。
正直、音楽を楽しんでいるお客さんの方にとっては、その音楽が東京のレーベルのものであっても、福岡のレーベルのものであっても、どこであっても、関係ないですし(笑)。だから僕たちは僕たちのスタンスで、お客さんに良いなと思ってもらえるアーティストや作品を、世の中に届けていきたいですね。
あ、あとは欲を言うなら、Hearsaysというバンドが福岡にいて、彼らもバンドを始めた初期からずっと見ているんですが、すごく良いんですね。だからどこか近いタイミングで東京でもライブが出来たりすると、もっと広がっていくだろうし、やっぱりそこも、広がっていってほしいなぁと思います。
Dead Funny Records
Official Website
Twitter
Instagram
Facebook