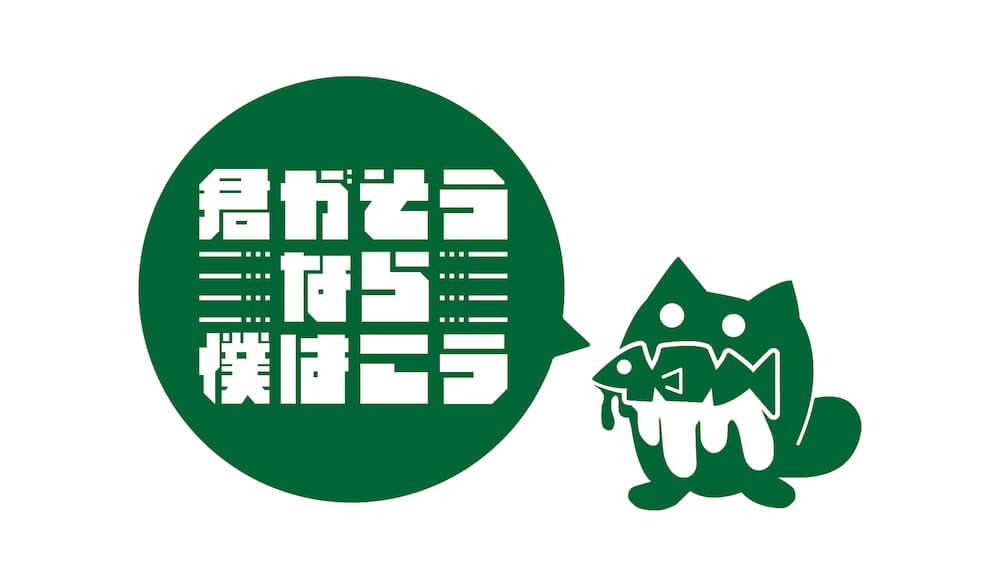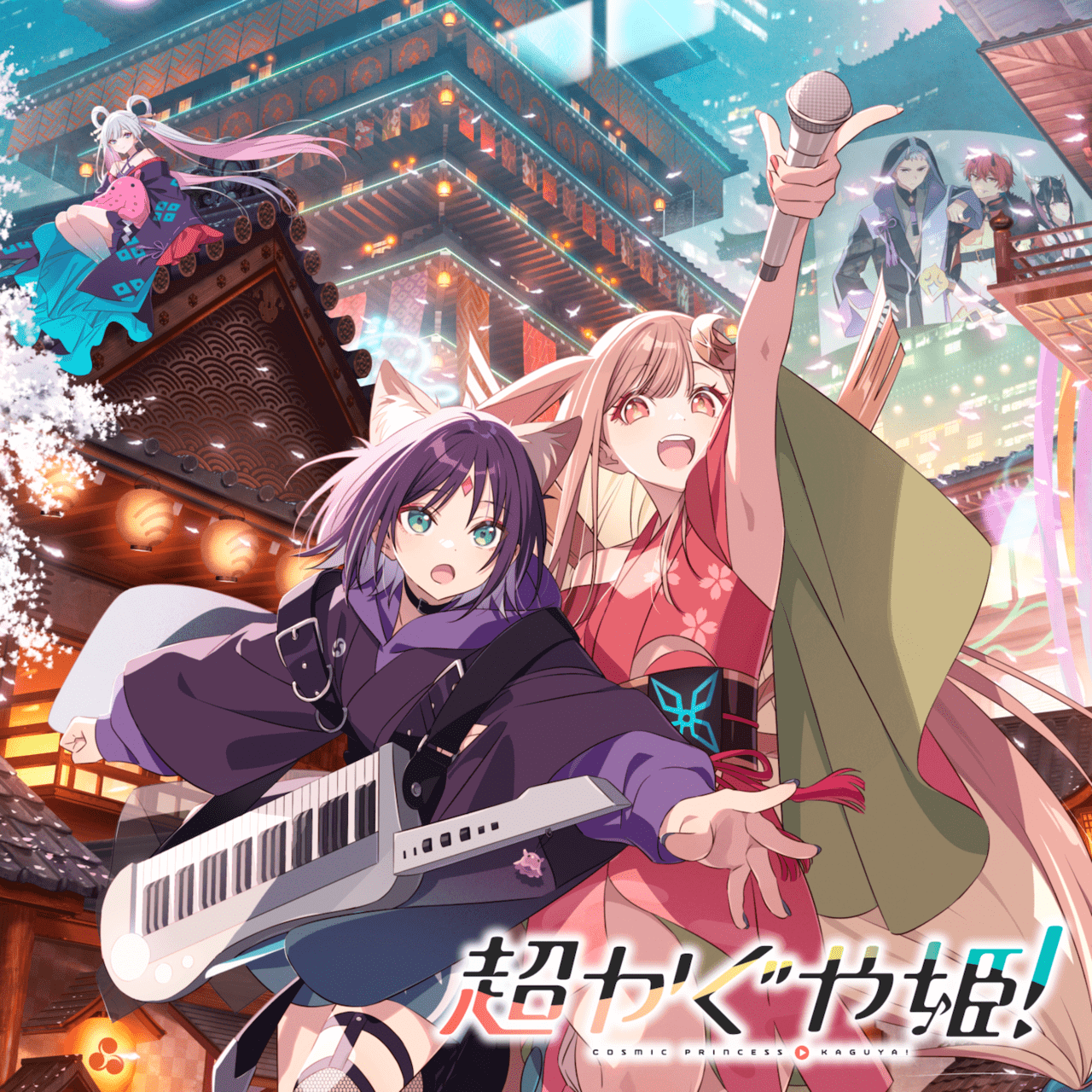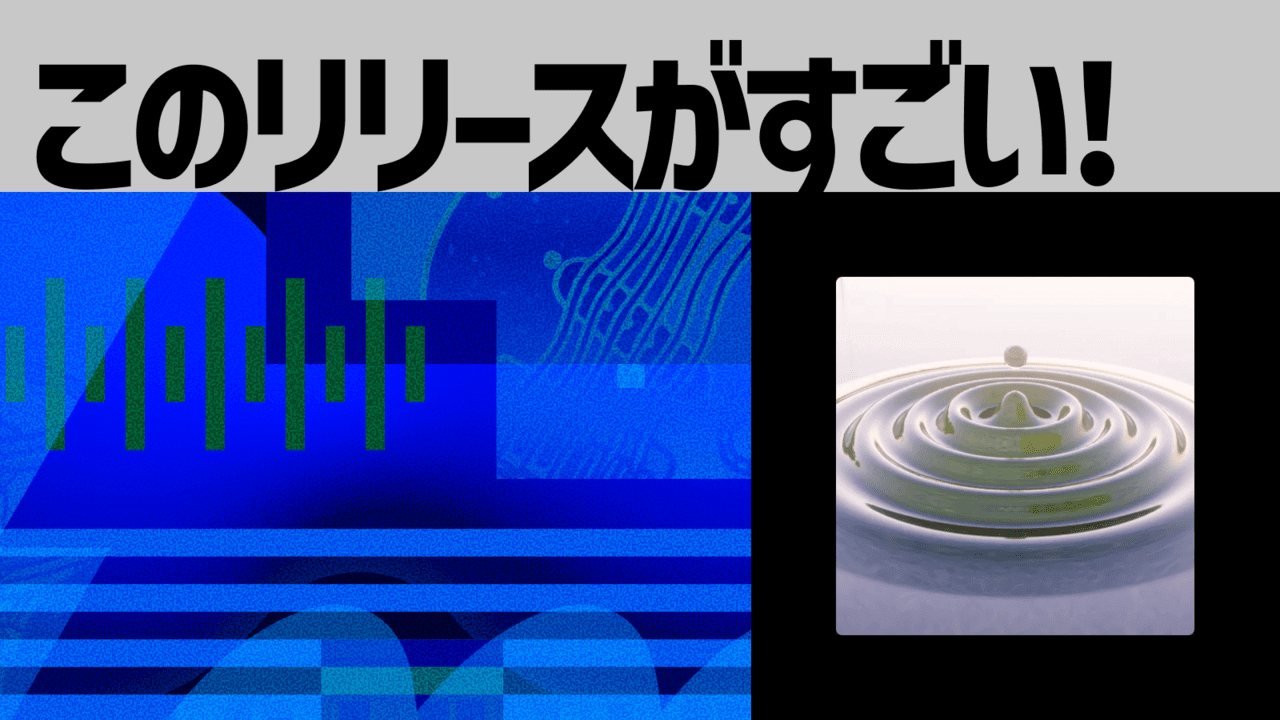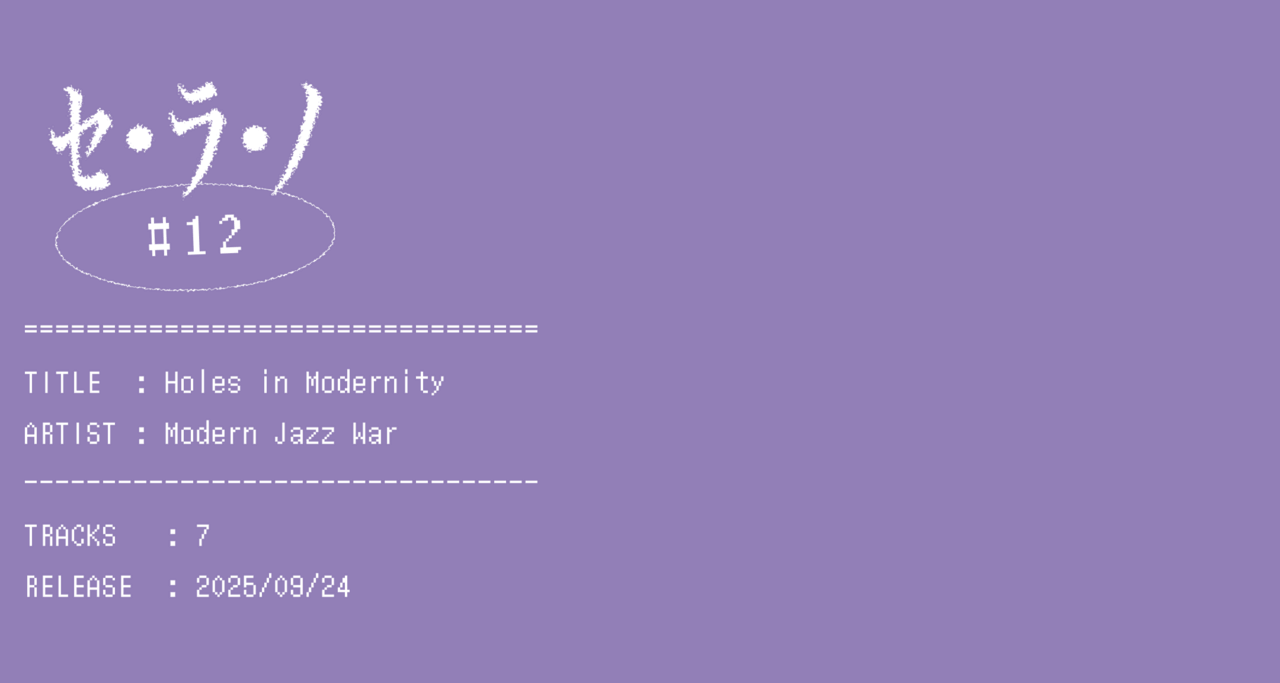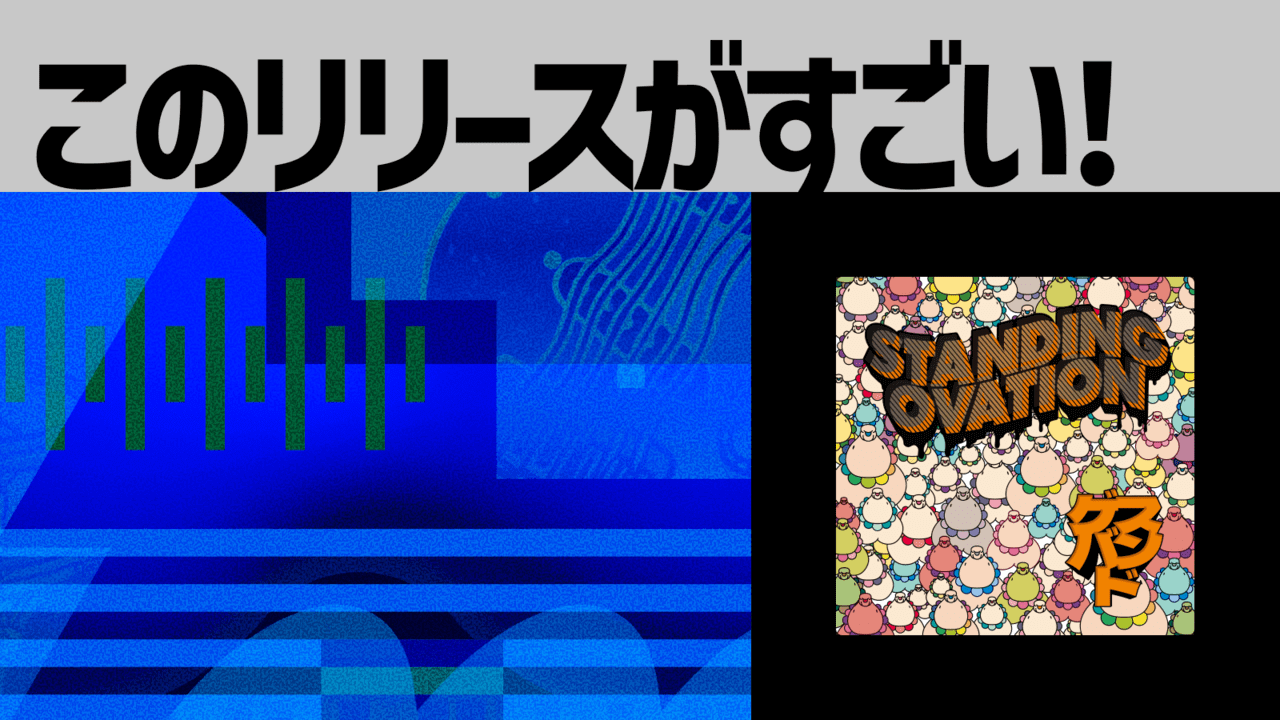d-iZe (ex-Goose house) インタビュー | 圧倒的な何かはなくても、できること


今回は、YouTube で話題の音楽グループ『Goose house』の元リーダー、シンガーソングライターの『d-iZe』さんへの、インタビュー。グループとして人気急上昇中の2014年にGoose houseを卒業し、ソロとして新たな道を歩み始めたd-iZeさん。2月24日には、ソロでのアルバム『IN A BEDROOM』をリリースしました。これからの活躍がますます期待される最中でのインタビューでしたが、そのお話は多岐に渡り、出てきたトピックスは、自身の考える音楽をとおした“エンターテイメント”についてや、アジアでのライブ活動について、そして“すっぴん風メイク”についてまで?あらたな道を歩み始めたアーティストへのインタビュー、お楽しみください。
アルバムタイトルにひそむ、本音
——ニュー・アルバム『IN A BEDROOM』、聴かせて頂きました。Goose house 時代から一貫した、d-iZeさんの“優しさ”がベースになっていながら、そこにあたらしい“強さ”を感じる作品だなあ、と感じました。
ありがとうございます!うれしいです。
——たとえば「フィクション」のように、メロディ・アレンジがすごくポップで柔らかくて、歌詞も一聴するとそれに寄り添った内容に思えるんだけど、よく耳を澄ますと、もっと内省的なこと、d-iZeさんの思考の核の部分を歌っているような気がして。
たしかに、そうですね。(Goose house 時代を含めて)今までつくってきた楽曲や作品に比べても、その“内側”を映した色合いが、強く出ていると思います。
今回アルバムのタイトルになった“IN A BEDROOM”という言葉が、ひとつのキーワードになっていて、最初から『外』を向いた感じの作品では、ないんですね。まずはすごく内側を向いて、自分と向き合いながら、生まれた作品というか。
——それがとても、新鮮でした。d-iZeさんのこれまでの活動を拝見すると、自分の近くにいるファンのみなさんを喜ばせたいというか、そういったみなさんに寄り添う音楽づくりをする、というイメージがあって。
はい。実際に、そういう気持ちは、すごく強いです。特にこれまでは、自分たちが楽しみながら、ファンの皆さんといっしょに楽しむこと、そこに何より一生懸命に取り組むグループ(Goose house)として活動してきて。

そして今、そのグループから離れて、「自分は果たしてなにが出来るんだろう」ということを模索しながら、去年1年間(2015年から音楽活動を再開)やってきて。今回、ほぼ全曲書き下ろしの新曲、というかたちでアルバムをリリースすることになったのですが、その作品の中に、今自分が感じていることや、思っていることを反映させたいな、という想いが強くあったんです。

実はちょっと、毒の量が多め
——なるほど。もう「スーパースター不要論」とか、衝撃だったんです。「こういう歌を、d-iZeさんが歌っちゃっていいの!?」という感じで。
ふふ、ヒヤっとするくらい、自虐的な内容だったりしますからね(笑)。
——ほかの歌詞も、すごいです。「すっぴん晒してあげる好感度」とか「キャプションなしじゃ数字稼げない」とか。
(笑)
——こういう内容を、ヒップホップのアーティストが世の中を皮肉ってる、とかだったら分かるんですけど、その渦中にもいるd-iZeさんが、真正面から歌っているっていう構図が、すごく面白くて。
ありがとうございます。ぼくは、インターネットから出てきた歌い手というか、YouTube 出身のアーティスト、というふうに、皆さんから認識して頂いていると思うんです。だから今回は、そういうものをあえて逆手にとって、自虐的に歌ってみる、というのはどうだろう?と思って作ったのが、この「スーパースター不要論」です。一聴するとポップですけど、実はちょっと、毒の量が多めなんですよね、今回のアルバム(笑)。
“圧倒的な何か”はなくても、できること
——今作で、その毒の量を多めにした経緯というか、内省的な想いを楽曲に込めるようにした特別な理由が、あるのでしょうか?
そうですね。ぼく、自分自身が「アーティストではない」と、いつも思っていて。どちらかというと、音楽も含めた“エンターテインメント”として、楽しんでもらえれば、という気持ちが強いんです。それは以前の活動から、一貫してあるもので。音楽だけではなくて、ツイッターでのやり取りとか、YouTube の動画とか、物販とか、ライブ後の握手会とか、そういうのを含めて、全部で楽しんでもらいたいなあと考えていて。
——以前から、その活動スタンスは、変わらないと。
はい。それで、そのスタンスってのが、どこから来てるのか突き詰めていくと、 きっと、自分に対する自信の無さなんだと思います。自分自身へのコンプレックスから来てる、と思うんです。元々、ぼく自身がすごく好きなアーティストは、本当に歌唱力が素晴らしかったり、ソングライティングにおいて比類なき才能を持っていたり、そういった洗練された“圧倒的な何か”を持っていらっしゃる方で。そういう憧れがある中、音楽活動をはじめてみると、その“圧倒的な何か”を自分は持っていないぞと気付いて、悩んだ時期があって。それはそれで、すごく辛かったのですが、活動を続けていく内に、良い意味での“あきらめ”が生まれたんです。
“圧倒的な何か”はないけれど、そうじゃない要素でも、みんなに楽しんでもらうことは出来るんじゃないか、と思い始めて。

——“圧倒的な何か”ではない要素や方法でも、みんなを楽しませられると。
それがきっと、音楽も含めた“エンターテインメント”として、提供する体験をみんなに楽しんでもらう、というスタンスに繋がっていきましたし、今までの活動の根幹をつくってくれました。たとえば、ぼく、ライブの後に握手会をやるんですけど、その握手会がすごく好きなんです(笑)。たくさんのひとに「ありがとうございます」と直接伝えることが出来るし。普段は会えない、色んなひとに会えるし。
——音楽を媒介として、色んな人に会うことが楽しみ、ということですよね。
そのうえで、今回の『IN A BEDROOM』では、そのエンターテイナー要素、ファンのみなさんが「欲しい」と思っていることを感じとってそれを演じる、をあえてシャットダウンして、そのあと自分になにが残るのかな?ということに、挑戦してみたんです。
それをシャットダウンしたときに、自分の中に曲として書きたいことってあるのかな?とか。「こういうこと言ってもらえると嬉しいよね」ではなくて、「ぼくはこれが言いたい」ということは、しっかり自分の中にあるのかな?と。それをすごく、自問自答して。その想いを、アルバムの中に反映させてみました。
その結果として、自分自身を自虐してみたり、優しいアプローチでちょっと冷めたことを言っていたり、Goose house 時代も含めて、今までのぼくのイメージだったであろう“爽やか”や“優しい”に対して、またジャンルの違う要素が混ざった作品になったと思います。
——今すごく、腑に落ちました。
あとは、どこかで窮屈さを感じていた部分が、あったんだと思います。その“爽やか”と“優しい”だけを演じている自分に対して。なにもこれは、音楽だけに限ったことではなくて。普段生きている中で、みんなそれぞれ『求められている自分』というものをきちんと演じることによって、世の中が円滑に進んでいく、とは思うんですけど。でも、たまにそうじゃない、「それだけじゃあないんだよ」という自分が顔を覗かせるときもあって。
——すごく分かります。
ですよね。「それだけじゃあないんだよ」って思うじゃないですか。そういうことを考えたときに、その「それだけじゃあないんだよ」という自分を出せる場所は、きっとみんなそれぞれの“BEDROOM”なんだろうな、とも思ったんです。なので、タイトルにある“BEDROOM”には、そういった意味も込められていますね。

それは、すっぴん“ふう”メイクのような
——ああ、たしかに。その“求められてる自分”と“それだけじゃあないんだよという自分”が、なんとかバランスを取り合おうとしているような楽曲が、今作は多い気がします。
まだまだ、難しいですけどね。この作品以外でもそこは、四苦八苦してます。今、「こっちはこういうものを見せたいんだ!」とか「こっちはこういうものを知って欲しいんだ!」という価値の提供の仕方って、そんなにお客さんは望んでいないんじゃないかな、と思うんです。これも、音楽に限った話ではなくて。お客さんは、自分自身でなんとなく見たいものを見るし、自分自身でなんとなく知りたいことを知ろうとする。基本的に“お客さんの方に選択肢がある”ということを認識していることが、すごく大切だと思っていて。なので、もう、せめぎ合いですよね、そこは。そのお客さんの“なんとなく”の欲求をどこまで汲み取って、どこまでの範囲であれば、答えることが出来るのか。なんというか、「すっぴん“ふう”メイク」のような(笑)。
——“ふう”だと(笑)。
すっぴんを求められるから答えるけれど、そこにもメイクという手は加えていて(笑)。たとえばですけど、ぼくは映像編集が苦手だし、ピアノを弾くのも実は苦手なんです。だけど、お客さんの中には、YouTubeで「ぼくがピアノを弾いて歌うのを見たい」と言ってくれる方がいる。
個人的な立場でいれば、苦手でやるのが嫌なこと、見せたくないことは、やらなければいいし、見せなければいいとも思うのですけれど、今、d-iZeというプロジェクトを進めていく中で、そこに関わってくれるひとたちも徐々に増えてきて。そうすると、個人的な感情よりも優先すべきことが、当然出てきますよね。「見たい」と言ってくれるひとがいて、自分の内側にも、取り組む理由が見つかる。そうであれば、たとえ苦手なことであっても、取り組むに値するのかなって。そんなふうに、思ったりします。
地方に出かけるようにアジアの国へ
——最後に、今後の活動や、展望について伺わせてください。ジャカルタでライブを行う予定とのことですが、今後は海外でのライブも積極的に行っていくのでしょうか?
そうですね。ジャカルタでのライブは、現地のプロモーターの方に、いきなりTwitterで「ジャカルタでライブをしませんか?」とオファーをもらって(笑)。でも、どうですかね、自分の中で日本以外のアジアにライブしに行くのって、それほど“海外”って感覚でもないんですよね。
——東京から、地方にライブに行くような感覚?
そうです、そうです(笑)。そんなに遠くないというか。アジアでのライブに関しては、特に台湾とインドネシアは、ずっと意識している場所で。Goose house 時代から、YouTube を通じて、ファンがすごく多くいるのも知っていましたし。実際に以前、オフで台湾の台北に遊びに行ったことがあったのですが、現地を歩いてたら、3回くらい声をかけられたんです。「YouTube のひとですか?」とか「このひとでしょ?」って自分が出ている YouTube動画をスマホで見せられたり(笑)。やっぱりすごく距離が近いな、と実感したんですよね。
——おおしろいですね。しかもそれは、「台湾やインドネシアに自分の音楽を届けよう!」という、特別なプロモーションをしていたわけではないんですもんね。
そうなんです。やっぱりそういう意味でいうと、YouTube で J-POP カバーを発表する、というところから、ぼくのことを結果的に知ってくれた方々が多くて。台湾もインドネシアのひとも、すごく日本の音楽、“J-POP”が好きなんですよね。ありがたいですし、「YouTube すごい!」って、あらためて思いますよね。だから“J-POP”という音楽フォーマットを生かして、海外で音楽活動をするということは、ぜひ挑戦していきたいです。台湾やインドネシアは、すでにもうJ-POPを好きでいてくれる音楽ファンが多い場所。そういった場所には、本当に日本の地方、福岡に出かけるような感覚で、どんどん歌いに行きたい、と思っています。
そのうえで、今はとにかく、『IN A BEDROOM』のツアーが楽しみです。2月末から東京の代官山でスタートして、全国6都市で公演があります。今回のアルバムは、ほとんどが書き下ろしの新曲なので、新しい曲をライブで歌ったらどんなことになるんだろう、お客さんがどういう反応をしてくれるんだろうか、ということのが、とても楽しみです。

d-iZe
Twitter
Instagram
Facebook
YouTube
Apple Music
Spotify
TuneCore Japan