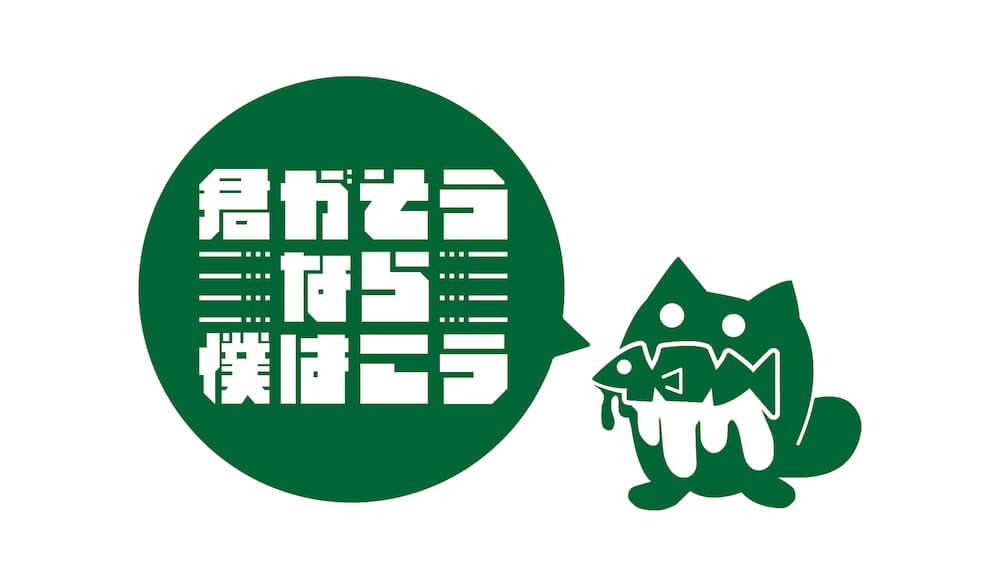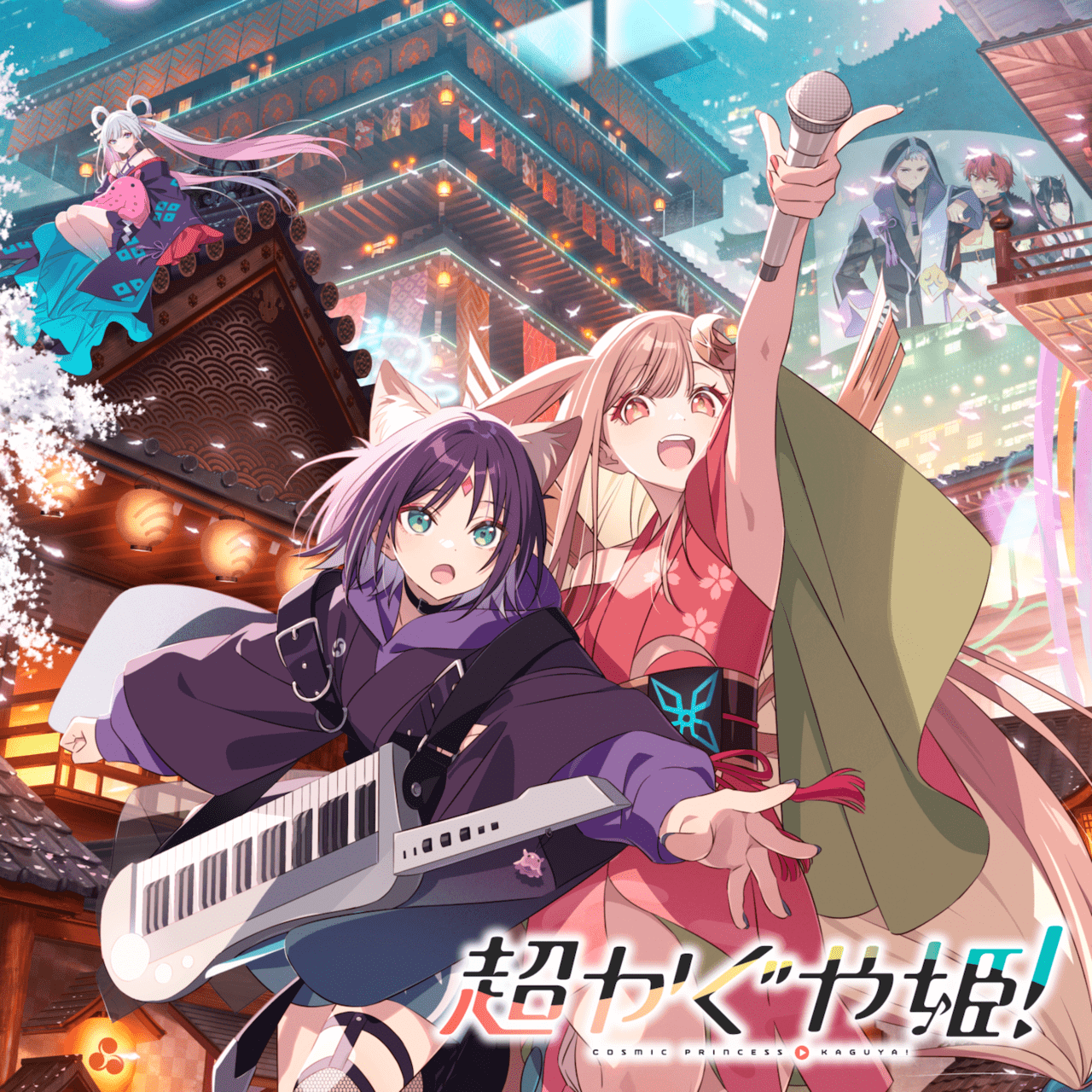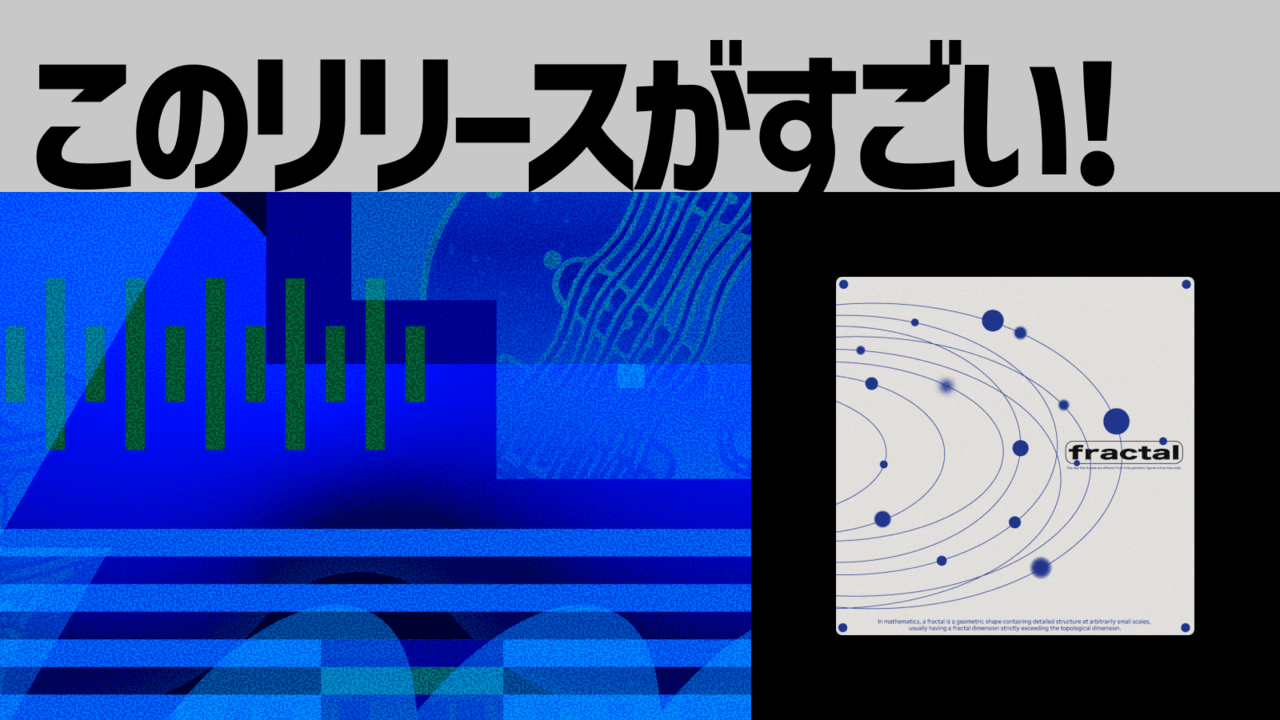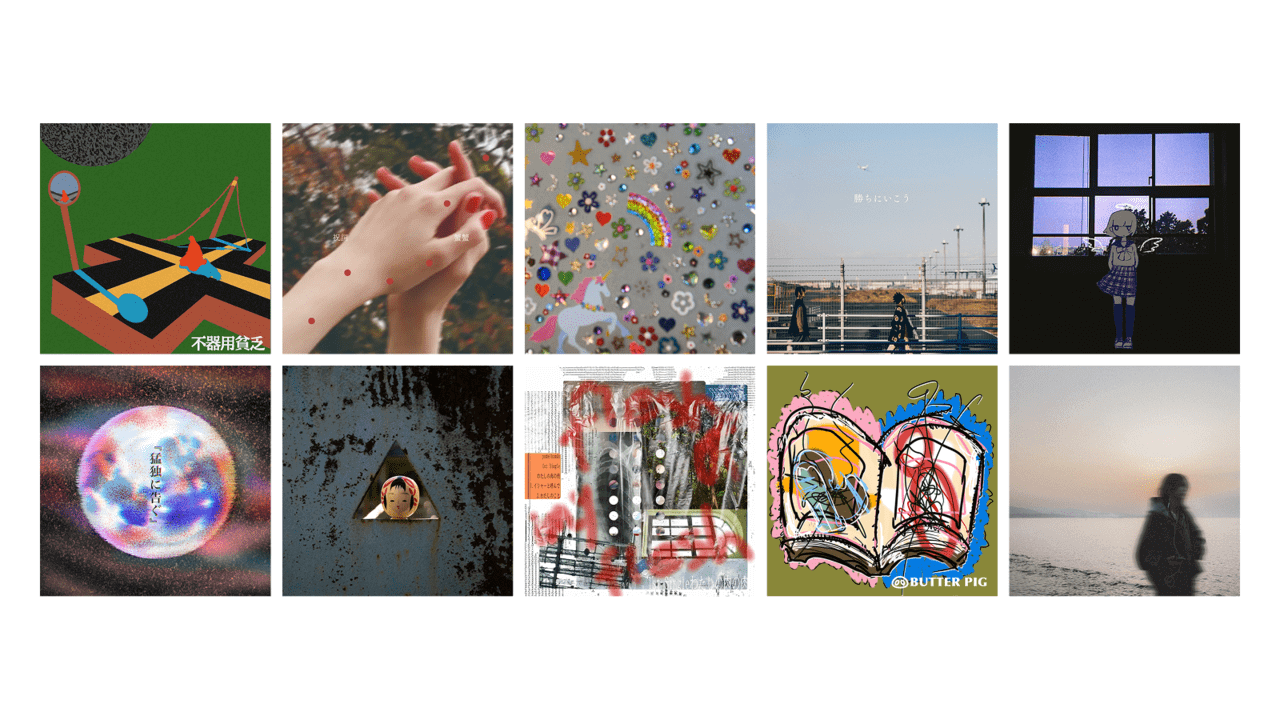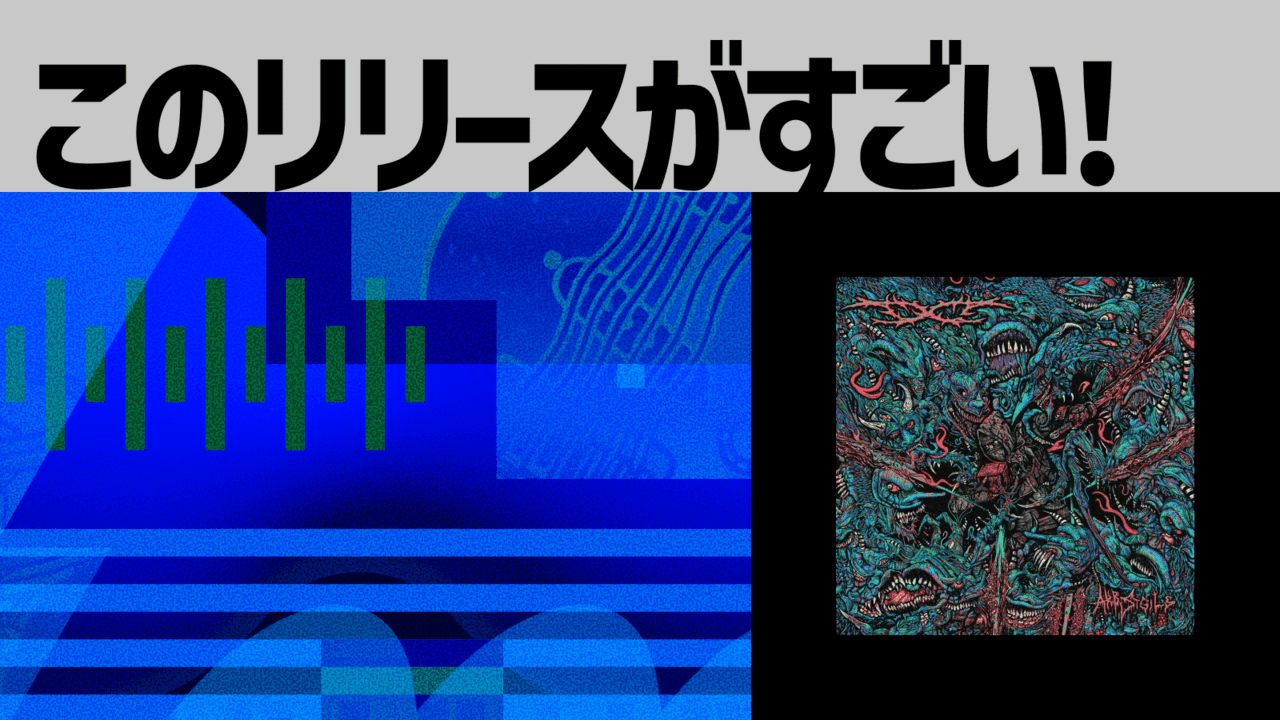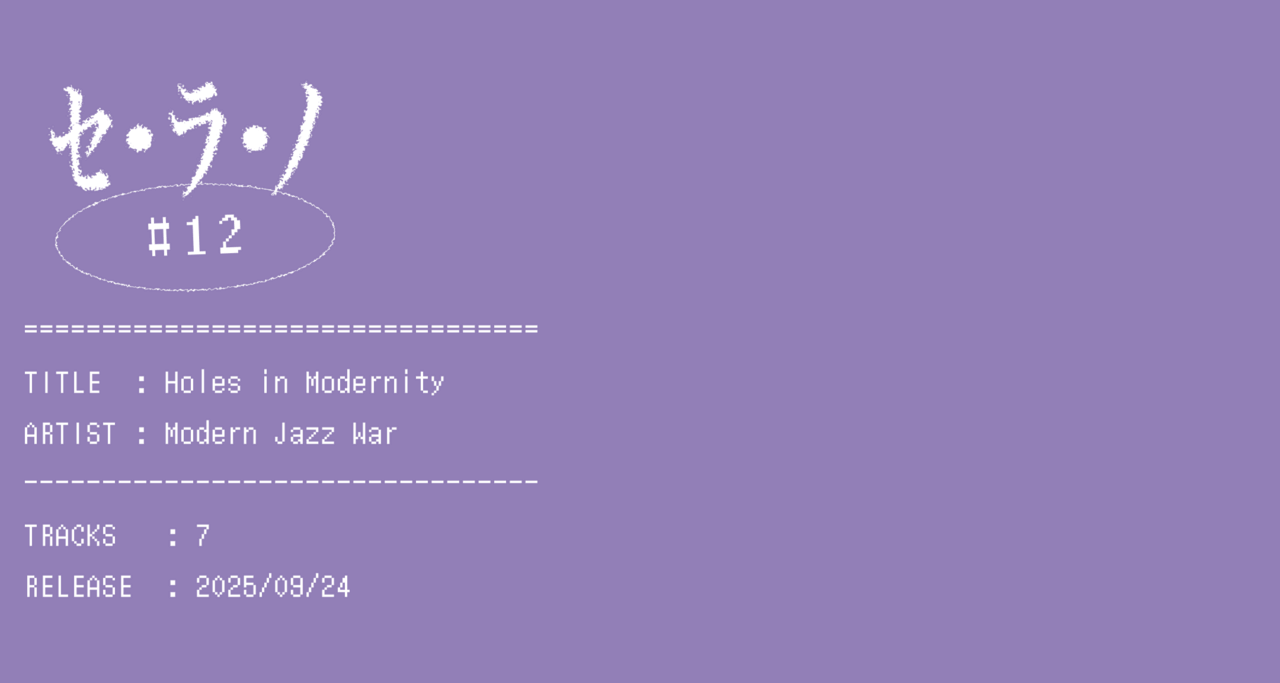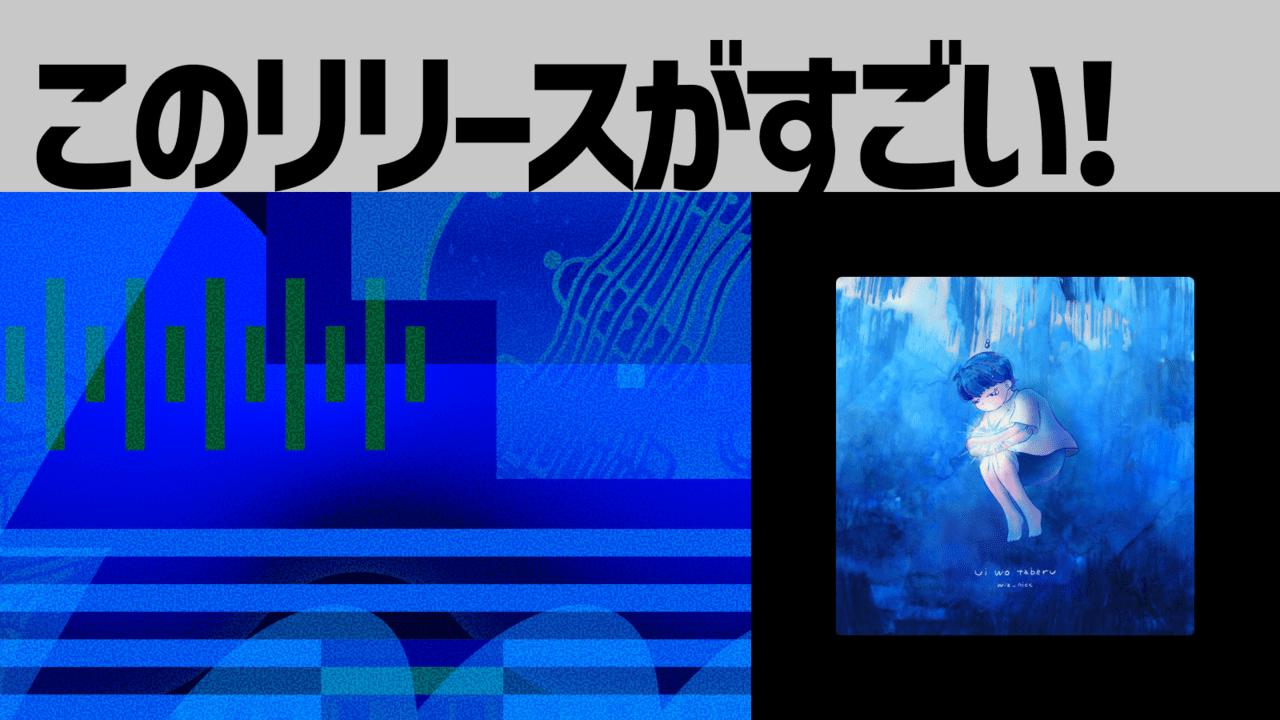JAKENインタビュー 2ndアルバム『SEA SIDE LAND』で描いた新たな景色、そして地元・広島での活動にこだわる理由

「Seaside Flow」「OMAE (feat. 百足 & 韻マン)」といったヒットシングルによって全国区の存在となった今も、地元・広島に根を張るラッパーのJAKEN。ステップアップを経て今年5月にリリースされたおよそ1年ぶりの2ndアルバム『SEA SIDE LAND』でもその勢いは健在。リアルかつユーモラスなリリックとメロディアスなフローに磨きをかけつつ、高層階へと視点をスライドさせ、覚悟と責任を背にリスナーを海風の吹く地へと導く。今回のインタビューでは、生まれ育った広島での活動にこだわる理由、そして音楽活動と並行して追い求めるもう一つの夢について明かしてくれた。
取材・文 : サイトウマサヒロ
音楽の力と、もう一つの夢
――ラップに興味を持ったきっかけは?
中学3年生くらいの頃に観た『高校生RAP選手権』がきっかけでした。そこでT-PablowさんからBAD HOPさんを知って、「Life Style」から楽曲も聴くようになって。その時代のHIPHOP少年たちにとって、王道のコースだと思います。ラップに出会う前はよくいる元気なサッカー少年で、めちゃくちゃワルかったというわけでもなく、活発な感じでした。それまで、音楽には全然縁がなかったですね。
――当時、BAD HOP以外にハマったラッパーはいましたか?
誰かっていうよりはバトル自体にハマってて、ニッチなバースを丸暗記して、友達とバトルの真似事をする時にバレないように自分のバースのように吐いてました。王道なバースだと、パクってるやんってバレるので。
――JAKENさんのバトル、観てみたいです。
今、それを考えてて。どこか大きい会場でやる機会が、確定ではないんですけどあるんじゃないかと。楽しみにしてもらえればと思います。
――おお、期待しています。その後、楽曲を作り始めたのはいつ頃だったんですか?
18の頃だったと思います。ラッパーを職業にしようとか、これで飯を食っていこうとかいうつもりでは全然なくて、遊びの延長線上みたいな感じで。全然そんなにちゃんとやってなかったですね。
――その頃のJAKENさんは、大阪の一二三屋で働いていたんですよね。
そうです。で、そこで繋がった韻マン君と一度真面目に話す機会があって。「この先の人生どうするんだ?」「ちゃんと音楽やった方がいいぞ」って言われて、僕自身もそこから本気になりました。スタジオに連れていってもらったり、楽曲の構成作りを教えてもらったり……ただの兄貴ですね。
――なるほど、韻マンさんとは大阪時代からの繋がりなんですね。
はい、出会って4年目くらいになりましたね。当時は夕方に起きて朝に寝るみたいな生活を送ってて韻マン君に怒られたんですけど、今考えると兄貴も同じように遊んでましたけどね、って思います(笑)。
――2023年5月にリリースされた「Seaside Flow」のバイラルヒットがJAKENさんの名を全国に知らしめるきっかけになりましたが、制作した当時のことは覚えていますか?
当時の自分のありのままを、カッコつけずダサい部分も含めてすべてを曝け出そうと思って作りました。ただ名前を知ってほしいというよりは、JAKENがどんな人物なのかを知ってほしいっていう、自己紹介の曲です。
――それまでの楽曲には見栄や飾った部分があったんですね。
昔は自分を大きく見せようとしてたんですけど、その時は別にお金持ちでもなかったですし、何かを成し遂げてるわけでもなかったので、どうしたってカッコよく歌えないんですよ。だから、いま何も持ってないこと、どうしようもない状態だけど頑張りたいという気持ちを、ストレートではなく面白い言い回しを使って表現しようとしたのが「Seaside Flow」です。良い曲が出来たなっていう手応えはありましたね。ここまでのヒットになるとは想像してなかったですけど。
――ヒットを実感した時はどう思いました?
TikTokでたくさん使われたんですけど、それが結構下ネタな部分だったので、「ここがバズるんだ」と思いつつ。それよりも前に「RETTER」(百足 & 韻マン feat. JAKEN)っていう楽曲にも参加してたので、初めてのバズっていう感覚はなかったんです。だから大きい驚きはなかったですけど、やっぱり人生が変わった瞬間だなと思いますね。これまでの人生でターニングポイントをいくつか挙げるとしたら、確実にその一つだと思います。
――「Seaside Flow」が多くのリスナーに届いたことで、音楽活動に対する姿勢も変わりましたか?
確かに変わったんですけど、人間的な成長としてはまだまだだったと思います。当時と今を比べると、音楽への向き合い方も、生活への向き合い方も全然違うなって。
――ということは、その後にも別のターニングポイントが?
ありました。「Seaside Flow」の後、満を持して1stアルバム『PUSHIN J』を出して全国ツアーを周ったんですけど、思ったより良い反響を得られなくて。もちろん聴いてくれる人がいて嬉しかったんですけど、自分としてはお客さんの入りも含めて厳しいツアーだった。そこで、もっと大きい規模でやるなら、音楽に向き合う姿勢や仕事に向き合う姿勢を大きく変えないとこれ以上の景色は望めないなと。それから生活も正して、お酒も一滴も飲まず、遊びにも行かなくなって。そうして出来た「OMAE」が一番のバイラルヒットになりました。
――ストイックな態度が結果に繋がったんですね。
「Seaside Flow」の頃にも未来へのビジョンはあったんですけど漠然としていて、実際に何をしたらいいのかが分かってなかった。改めて目標を自分に問いただして、その達成のために1年後、半年後、今週、今日と細分化してやるべきことを考えるようになってから、一日の行動も変わって、仕事も音楽も上手くいくようになったと思います。
――その、「仕事」っていうのは?
詳しいことについてはまだ話したくないんですけれど、僕はいま会社をやっていて、20人弱の従業員も抱えてるんですよ。ここで言ったら叩かれるかもしれないんですけど、最年少で上場することに強い憧れがあって。最年少はともかく、創業者として上場企業を作ることは大きな目標の一つです。
――それは、音楽とはまた別の夢というか。
そうですね。音楽の力って、みんなのやる気が高まるとか癒しになるとか、心情的な部分に対してのアプローチだと思うんですけど、起業は解決したい社会問題に直接取り組むことができるので。
――たしかに。
音楽をやってて一番嬉しい瞬間って、ヒットを記録したり大きいお金が入ってきたりした時ではなくて、「救われました」とか、「学校に行けるようになりました」「頑張る力を貰えました」みたいな言葉をかけてもらう時なんですよ。その言葉に僕自身も救われてるし。それを、きれいごと抜きで、もっと大きい力、大きい範囲で達成できるのが起業だと思ってるんで。社会に対してポジティブな影響を与えて、みんなから感謝されて終われるような人生を送りたい。
――起業を通して社会に働きかけつつ、音楽ではよりメッセージにフォーカスしたい?
はい。まあラッパーらしいフレックスはかなりしますけど、別に誰かにマウントをとって自己顕示欲を満たそうとしてるわけじゃなくて。22歳で高層マンションに住んで、スーパーカーに乗って、好きなアクセサリーを着けて……僕が普通に田舎におった頃って、そんなヤツおらんと思ってたんですよ。できるわけないだろと。でも、まだ地方に住んでる僕がそれを見せることによって、若い子たちが「俺らもできるじゃん」って感じられたらいいなと思いますし。逆に腹立って「俺もやったらぁ」ってなっても嬉しいです。